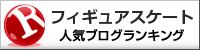番組公式HPは「こちら」。
NHKの「3か月でマスターする」シリーズは、趣味から学問から幅広いジャンルに及んでいることは知っていて、私も「江戸時代」のシリーズは何話か見たことがあるんです。で、家族がたまたま録画していた「(2)手を伸ばしたくなるリンゴ~立体感の秘密~」を何気なくテレビで流していたら、感動と衝撃を受けましたね!NHKプラスでこの第二回放送は配信されているので、ぜひチェックしてみてください。
この第二回放送は、画家の柴崎春通先生がタレントの山之内すずさんとともに「水彩画でりんごの絵を描く」というもの。筆の使用はほぼ1本のみで、最終盤で細い筆をもう1本使っていたので、計2本でしたね。いたってシンプルなんですけど、先生のアドバイスが凄いのはもちろんなんですが、「絵を自力で描くことの奥の深さと素晴らしさ」に感動しました。
以下、ネタバレになりますので、興味のある方は先に番組の方をご視聴ください。約30分間の番組で、NHKプラスの配信期限は「4月16日(水)午後9:59まで」です。
・りんごの写真を手元におきながら、まず鉛筆でラフなデザインを描いていきます。特に「暗い部分と明るい部分の塗り分けをどうするかの基本方針」を、鉛筆の段階でかなり明確に決めています。鉛筆で詳しく塗り分けているのではなく、「どこが一番暗くて、どこがそこそこ暗くて、どこが一番明るくて」という箇所を決めておく感じです。
・絵の具で描いていきます。パレットに出している色数は、「赤・オレンジ・やまぶき色・黄色・青・青紫・黒・白」で、まずはりんごの赤い部分を赤色中心で塗っていく。暗い部分は赤に黒を混ぜた色で塗っていきます。で、上述の「明るい部分・そこそこ暗い部分・暗い部分」という方針にしたがって、色を調整しながら塗っていくんですが、「暗い部分を一度塗ったらそこは終わり」というわけではありません。例えば、リンゴの下半分は「赤&黒」で混ぜた色で一度塗った後、パレットで色を微調整した「別の色」で重ね塗りします。この作業によりりんごのゴツゴツとした「立体感」が生まれます。
・たしかに「一度塗ったらそこは終わり」だったら塗り絵と同じなので、「これが水彩画というものなのか・・・」とハッとさせられました。図工や美術の授業でたぶん習っていたテクニックなんだと思いますが、小中学生の頃の私がその技術を明確に意識して絵を描いた記憶はまったくありません。そして、あらかじめ水の量についてアドバイスがあったのか、私がイメージしていた水彩画よりももっと油絵に近い印象を受けました。
・こうやって文字にするとどうってことなさそうですが、この「重ね塗り」の作業を丁寧に取り組めば、どんどん絵がリアルでなおかつ味が出てきます。これってやっぱり、先生が隣にいて、一緒にりんごを描いているからこそ、その重ね塗りの重要性が分かるんだと思います。先生のお手本の絵や、あるいは写真を見て、ひとりで黙々とこれができるかというと、私には無理だと思いました。
・微妙に色を変えた重ね塗りは、色の変化が楽しめるので、漆塗りとは違う。たとえ初心者でもやればやるほどりんごの絵に味が出てくる。これが書道の場合、「ひと筆で上手い字を書くもの」ですから、一発で上手い字を書くためにひたすら練習の日々。この練習の辛さが「合わない」人もいるはずです。
・仕上げの段階で、りんごの「白いポツポツ」を細筆で足していくんですが、このポツポツも「白で足しておしまい」ではありません。微妙に色を変えて何度も足しているんですね。
この講座を見ていて思ったのは、「同じ画像」「同じ写真」を見ているはずなのに、しかもそれを一緒に水彩画で写実的に描くはずなのに、絵にするためのプロセスがその人の感性によって違ってくる。基本的なテクニックを押さえつつ、あとは自由でいい。二人が楽しみながらリンゴを描いているので、完成したお二人の絵を見て、そりゃ先生はさすがの出来なんだけど、すずさんの絵がダメとか下手とかまったく思わなくて、彼女はこういう風にりんごを見て、明るい部分・暗い部分をこう感じたのかぁ・・・と、すごく味のある仕上がりに感じました。
アプリで盛れたり、AIでアニメ風に加工できる時代ですけど、自力で絵を描くことの尊さと、その人の自由な感性によって「違った味」が出る水彩画って素晴らしいな!と感激しましたね。こう言っちゃ大袈裟かもしれないけど、昨今の閉塞感漂う空気を爽やかにしてくれるというか、硬直化した価値観を変えてくれるような番組だなと思います。
では、また明日!
Jun