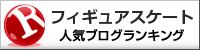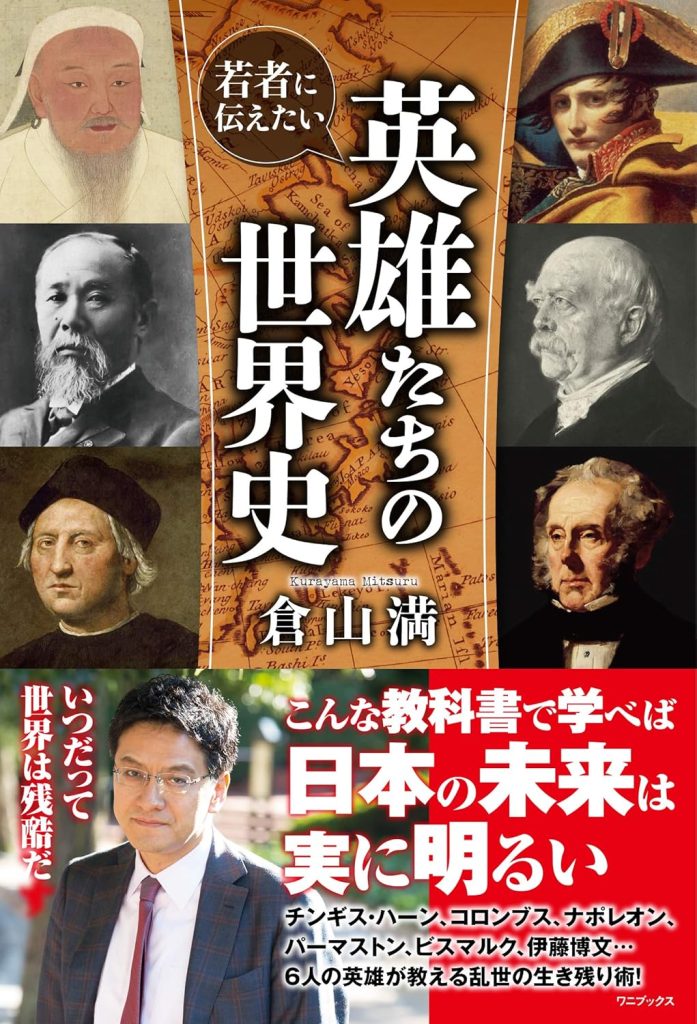
通常、もともと買う予定だった本の場合、書籍版での購入がほとんどなんですが、ついつい電子書籍で衝動買いしてしまったのが、倉山満著『若者に伝えたい 英雄の世界史』でした。
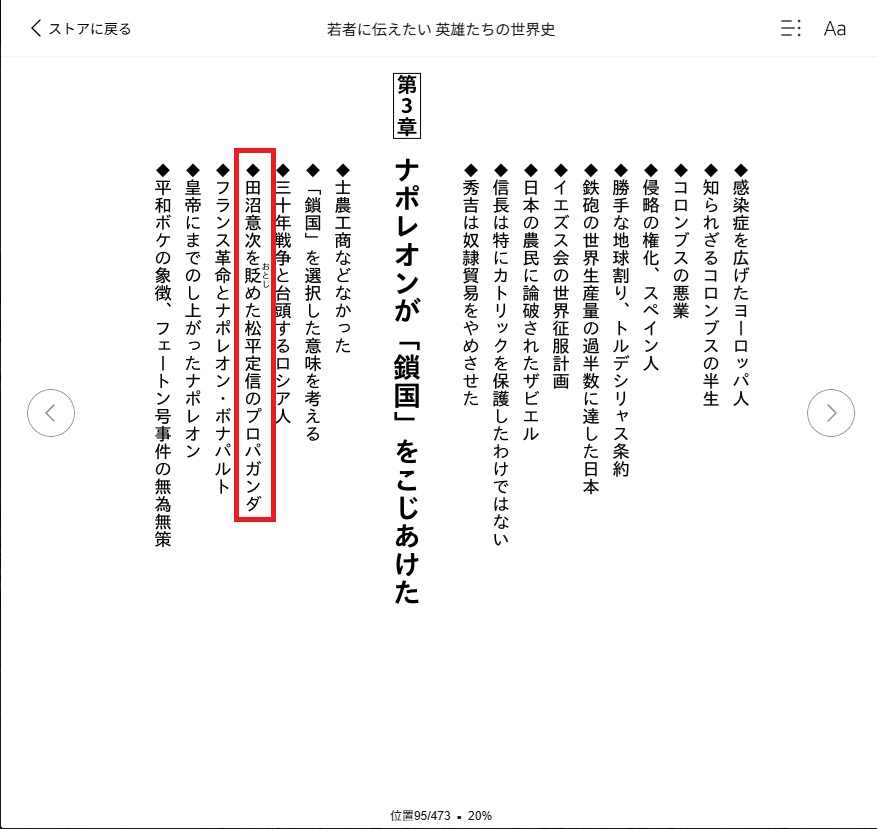
まだ一部しか目を通していませんが、なぜ衝動買いしたかと言うと、上の目次の「◆田沼意次を貶めた松平定信のプロパガンダ」という部分なんです。現在放送中の大河ドラマ「べらぼう」では、田沼意次を演じるのは渡辺謙さん、そして松平定信(幼名・田安賢丸)を演じているのが寺田心君です。本文の中ではこのような記述がなされています。
田沼意次は長らく「日本史の三大悪人」の1人とされてきました。20世紀にようやく、大石慎三郎先生が名誉回復を図りました。これも江戸時代研究の進展がもたらした成果の1つです。実際、田沼の時代の経済は絶好調でした。文化も栄えます。意次は開明的な人物で、今では「資本主義を用意した最初の日本人」と評されています。経済に道徳を持ち込む江戸時代の人は、「儲けることは卑しいことだ」との固定観念に憑りつかれています。「経済を振興させてこそ国力が上がる」と考える田沼は嫌われました。
田沼意次は既得権益を打破しようとした成り上がりです。それだけに、まわりからの風当たりが強く、「賄賂政治家」とレッテル貼りがされます。このレッテル貼りは、田沼意次失脚後に寛政の改革を行った白河藩主松平定信のプロパガンダです。この松平定信こそ真の悪人で、尊王家のフリをするだけよけいに質が悪い見本のような人です。田沼意次がやり始めた画期的な事の数々を、松平定信が潰してしまいます。
松平定信が行った政策を、大石慎三郎先生は「元祖ポルポトともいうべき政策」と評しています(大石慎三郎『将軍と側用人の政治』講談社現代新書、1995年)。そこで槍玉にあげられているのが、「寛政異学の禁」「文化に対する弾圧」「棄損令」です。寛政異学の禁とは、官学の朱子学以外を禁じる命令です。文化に対する弾圧では、浮世絵や好色本を発禁にしました。棄損令は、武士が商人にした借金を棒引きにさせる命令です。さらに、飢饉で苦しむ民衆を放置していました。頼るものが無い民衆は、京都の天皇陛下にすがる「御所千度参り」を行いました。
ちなみにポルポトとは、カンボジアの独裁者であらゆる文化を破壊し、国民の4分の1を虐殺しました。「勉強なんかすると人を不幸にするから、本をすべて焼く」「眼鏡をかけている奴は勉強ばかりしているに違いないから死刑」「美人は人の心を惑わすから死刑」という調子で、国民を殺してまわりました。松平定信は、さすがにそこまではやっていません。日本人で良かったとつくづく思います。
「悪人」とか「ポルポト」というのは誇張した表現ではあるけど、「国難の際に国民(民衆)に規律を押しつけるタイプ」ってのは分かる気がします。いまの日本で言うと、不況だろうが感染症が拡大しようが天災が発生しようが、「孫子の代にその苦しみを押しつけてはいけない!」と必要な援助を出し渋って増税しようとする政治家・官僚が頭に浮かびます。大河で今後彼がどのように描かれるか不明ですが、寺田君のここまでの演技は、「自分はいつだって正しい」というエリート風を吹かせてる感じが出ているので、そのような歴史認識で制作されているのかもしれません。
という訳で、上で引用文献として挙がっていた大石先生の著書を注文しました。いまから楽しみです!
では、また明日!
Jun